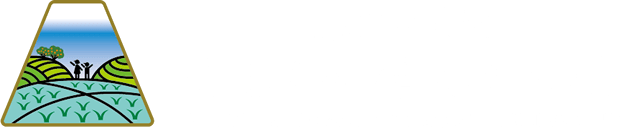平成24年度登録

 平成24年度 知事顕彰受賞
平成24年度 知事顕彰受賞- 地域名・施設名
千框(せんがまち)の棚田(せんがまちのたなだ)
- 所在地:
- 静岡県菊川市倉沢1121-1地図
- おすすめ
- 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」/県棚田等十選「千框の棚田」/あぜ道アート
- URL
- http://www.tanada1504.net/
- ブログURL
- http://www.tanada1504.net/sengamachi/
- 駐車場
- 有(上倉沢公会堂の道を挟んだ向側に数十台、せんがまちの棚田を見下ろす道沿いに5台程度)
- アクセス
- 【車】東名高速相良牧之原I.C→国道473号バイパス島田・空港方面→倉沢I.C→上倉沢公会堂(相良牧之原I.Cから約10分)

「千框(せんがまち)」って?
かつては3000枚もの小さな田んぼがモザイク模様で広がっていた上倉沢地区。千枚の田んぼという意味で「千框(せんがまち)」と呼ばれています。昭和50年代にその数が激減しましたが、かつてのような美しい姿を思い描きながら、地元NPO、学校、棚田オーナー、大学生、企業などが協力して複田、保全活動を行っています。農作業を通して世代・所属を超えた、和やかな交流が生まれています。ムシやカエルが触れなかった子供たちも、いつの間にか生き物と仲良しになっています。中には大人顔負けの生き物博士になっているお子さんも。
先人達が残してくれた、せんがまちの宝を一緒に守っていきませんか。詳しくは棚田いこうよ.netをご覧下さい。

棚田風景あれこれ
田植えの後の水鏡、真夏は鮮やかな緑、稲穂が頭を垂れる頃には金色と、棚田は四季折々に様々な表情を見せてくれます。水の流れる音、キジの鳴き声、カエルの合唱、風が稲穂を揺らす音。耳でも楽しめます。3月には「あぜ道アート」が開催され、揺れる蝋燭の光により幻想的な雰囲気が楽しめます。農作業の合間に空を見上げると、静岡空港を発着する飛行機が見られることも。JR東海道線菊川-金谷間は電車の車窓から棚田が見える珍しい区間です。電車をご利用の場合は、その瞬間をお見逃し無く!

生き物にも温かいせんがまちの邑人
千框では「冬水(ふゆみず)田んぼ」と言って、田んぼを起こす前に水を張ります。土が乾き、田にヒビが入って水が漏れないようにする効果と、生き物の「ゆりかご」の役目があります。
また、千框の棚田に隣接するのは世界農業遺産「静岡の茶草場農法」に欠かせないススキ等が生えた採草地(茶草場)です。こうした自然環境が生物の多様性を育み、冬に水中で産卵する静岡県の絶滅危惧種ニホンアカガエルなども生息する貴重な場となっています。その小さな命を育むため、作業とは関係なく早い時期に水を入れたり、水路にカワニナの餌となるメロンの皮を何気なく1枚入れてあったりと、地元の人々の生き物に対する心の温かさが伝わってくるエピソードもあります。
生き物たちの環境を良くする事が、人間にとっても大切なこと。豊かで多様な生態系をめざし、静岡大学棚田研究会も協力してビオトープを製作しています。